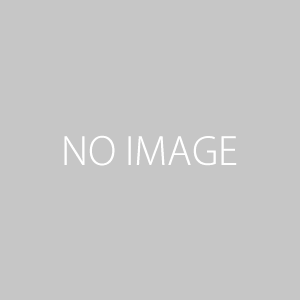『シッラ』はヘンデルの美しい音楽がぎっしりつまったオペラ。「イタリアの美しい音」を音楽堂のすみずみまで届けたい。ファビオ・ビオンディインタビュー by加藤浩子
『シッラ』はヘンデルの美しい音楽がぎっしりつまったオペラ。「イタリアの美しい音」を音楽堂のすみずみまで届けたい。ファビオ・ビオンディ インタビュー by 加藤浩子(音楽ライター)
バロック音楽発祥の国イタリアに生まれ、世界の「古楽」ブームを牽引するリーダーの一人として活躍するファビオ・ビオンディ。古楽オーケストラ「エウローパ・ガランテ」を立ち上げ、ヴィヴァルディの『四季』のような超有名曲から埋もれたレパートリーの発掘まで、幅広い分野に情熱を捧げてきた。2006年と2015年に神奈川県立音楽堂で日本初演された2本のヴィヴァルディ・オペラは、才人ビオンディの真髄を知らしめた名演として大絶賛。来年の2月には、3作目としてヘンデルの『シッラ』が上演される。もちろん日本初演だ。イタリアにおける「古楽」から『シッラ』の魅力まで、古楽シーンをリードする注目のマエストロに存分に語っていただいた。
―イタリアはバロック音楽やオペラが生まれた音楽の国ですが、聴衆の趣味は保守的だという印象があります。そのようなイタリアで「古楽」ブームを担われていますね。
イタリア人はオペラを愛しているのですが、決まった作曲家の決まった演目を好む傾向があります。主に19世紀の、ロッシーニ、ヴェルディ、プッチーニといった作曲家の有名作品ですね。バロック・オペラやマイナーな作品は、フェスティバルでの上演ならいいのですが、ふだんの劇場のレパートリーにはなりにくい。
でも、私の前にも「古楽」に関心を持ったイタリア人アーティストはいました。パイオニアは、1970年代にボローニャの歌劇場でヴァイオリン奏者をしていたルイジ・ロビーギです。ちょうどヨーロッパで古楽ブームが起きていて、レオンハルト、アーノンクールといったアーティストが活躍しており、彼らの影響が大いにありました。
―ビオンディさんの「古楽」との出会いについて、具体的に教えていただけますか?
1976年に、レオンハルトとアーノンクールの『マタイ受難曲』を聴いたことはとても大きかったです。ルーティンの演奏に限界を感じていたので、作曲家や時代が何を求めていたのかを考え直し、フレージングやアーティキュレーション、デュナーミク、様式などをきちんと追求するべきではないかと思い始めました。それが自分にとっての古楽のスタートです。今の古楽界はちょっと新しいものを追い求めすぎて、アナーキーになっている傾向がありますが、重要なのは「作曲家」であり、演奏家の自己表現ではないことを忘れてはいけません。
イタリア人の個性は「美しい音」の追求
―「古楽」を追求するにあたって、お手本にした方はいますか?
基本的には仕事と並行して、つまり研究が進んでいる団体で演奏することで学びましたが、「師」と言えるのはエンリコ・ガッティというヴァイオリニストです。彼は「イ・ムジチ」のメンバーでした。「イ・ムジチ」は古楽の団体ではありませんが、私たちの「エウローパ・ガランテ」との共通点はあります。それは「美しい音」の追求です。それこそイタリア人の個性なのです。
「古楽」というと、「音が美しい」という印象はあまりありません。けれど私たちイタリア人は、丸く、やわらかく、暖かい「イタリアの音」、「美しい音」を求めます。それは楽譜から読み取ることができる。私たちイタリア人ヴァイオリニストの先達である大作曲家、コレッリもジェミニアーニもヴェラチーニも、みな「美しい音」を奏でていたはずです。
『シッラ』はヘンデル初期の美しい音楽の集大成
―音楽堂でのバロック・オペラですが、これまでの2回はイタリア人のヴィヴァルディの作品、『バヤゼット』と『メッセニアの神託』を取り上げられました。
『バヤゼット』は、ヴィヴァルディの充実期に作曲された作品です。キャリアの晩年、1730年代に書かれていますが、ヴィヴァルディは当時自分が時代遅れになったと感じていて、様式を変えようとし、それに成功して音楽がとても豊かになった作品なのです。『メッセニアの神託』も充実期の作品で、彼のヒットパレードのような作品ですね。
―なぜ今回、ドイツ人でイギリスに帰化したヘンデルの『シッラ』というオペラを選ばれたのですか?
ヘンデル初期の美しい音楽の集大成といえるオペラだからです。ロンドンに来て『リナルド』で最初の大成功を収め、神のように崇められていた、ヘンデルの幸せな時代の作品でもあります。楽譜もほぼ残っていて、第3幕の海での嵐のシーンなどほんの一部の欠落はありますが、ヘンデルのほかの作品から転用して補うことができます。ヘンデルには『ジューリオ・チェーザレ』など有名なオペラもありますが、今の聴衆は知的だし、聴衆の方の立場からしても、色々なレパートリーを知る方が面白いのではないでしょうか。
上演時間が2時間と短いのも、聴衆にとっては利点なのではないかと思います。上演中に飲食やおしゃべりをしていた当時と、舞台に集中して聴くのが当然の今では、聴き方が違います。ヘンデルの他の有名オペラだと、4時間も集中しなければならない。『シッラ』は短いけれど美しく、カットしないで上演できる理想的なオペラです。
『シッラ』が短いのは、劇場のために書かれた作品ではないからです。おそらくバーリントン邸での私的な催しのために作曲され、招待客だけが聴くことができた。台本がやや乱暴なのは、そのせいもあるのではないでしょうか。けれど音楽はとても充実しているので、大半が『アマディージ』というオペラに転用され、一般の聴衆に開かれたのです。
2017年にこの作品を初めて演奏し、録音もしましたが、「音楽が美しい」と絶賛されました。
―今回は彌勒忠史さんによる演出がつくのですね。
ええ。彌勒さんとは『メッセニアの神託』で共働し、とてもうまくいったので今回もお願いすることにしました。小さなオペラですが、場面を作る時には色々な効果が必要だし、スペクタクルな部分もあります。最後のどんでん返しがあっという間に起こってしまうなど物語にわかりづらい部分があるので、それを補う意味でも演出が重要ですね。シッラが独裁者であることを、聴衆にわかってもらわなければなりません。「権力のおかしさ」を見せなければならない。そして最後にたどりつくのは「愛の勝利」です。日本ならではの演出も取り入れられたらと思っています。
―初演の時はカストラートが歌った役は、女性が歌うのですね。
ええ。カウンターテノールを使う指揮者もいますが、カウンターテノールはいわば現代の発明。女性の声のほうがファルセットを使わない分「自然」だし、カストラートの声に近いと考えます。最後のカストラートだったモレスキの録音が残っていますが、女声のように聴こえますよ。
―バロック・オペラでは即興や装飾がとても重要です。
そうですね。バロック音楽の価値はそこにあるのではないでしょうか。以前はバロック音楽は退屈と思われがちでしたが、今は即興や装飾が復活したおかげで面白いと受け止められています。
ヘンデルの時代のカストラートは、歌手の即興や装飾をすべて自分でやっていましたが、書かれた時代や場所によって即興のやり方、様式が違うので、どこでどんな風に書かれたかということまで考えなければなりません。ですので、70%は私が考えます。楽器の装飾や即興については、その場でやります。お楽しみに!
my hall myself
私にとっての神奈川県立音楽堂
音楽堂は劇場のサイズも、歌手とオーケストラが同じ高さで演奏できて完璧な一体感が得られる点でも当時の劇場に近い空間です。音響もとてもいいので、歌手の丸くてやわらかい声がすみずみまで届くところも気に入っています。モダンな劇場は大きすぎるし、オーケストラがピットに入ってしまうと、声が大きいことのほうが重要になってしまう。それでは、声の「すべて」を届けるのは難しいですからね。
「神奈川芸術プレス」Vol.150(2019年9月15日発行)表紙・巻頭インタビュー「Creator’s Voice」より転載
取材・文:加藤浩子 撮影:藤原亮子